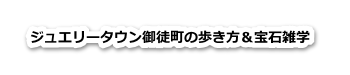アンティークジュエリーと呼べる時代

アンティ−ク・ジュエリーの年代
アンティークジュエリーとは、アールデコが終わる1930年頃より以前に作られたものを”アンティーク・ジュエリー”として扱うのが一般的と思います。
アールデコ以前のそれぞれの時代には、個性のある特徴を備えたデザインや材料があり、1800年頃からジュエリーは各国で盛んに作られ、それぞれの時代区分があっても良いのですが、その時代に最も多くのジュエリーを作っていた英国を基準として年代を区切って説明していくことにします。
なお、フランスのようにナポレオン時代や第二帝政期の様式、さらにはカルティエのガーランド様式や、各国のオリジナルジュエリーなど、その時代を風靡した独自性を強調するものや、1800年代以前に作られた、ギメル、フェデ、ポージーリングなどの今に続くデザイン様式もあります。
また、ジュエリーは太古の昔から人類とともにあったのですから、エジプトやアッシリアやインカのアンティークジュエリーがあってもよいのですが、耐久性やデザインなどの感性からいっても、現在でも使用することを基準とした場合は19世紀初頭くらいからになると思います。
1800年頃〜1837年 ジョージアン期
1837年頃〜1901年 ヴィクトリアン期
1880年頃〜1914年 エドワーディアン期
1901年頃〜1914年 アールヌーボー
1920年頃〜1930年 アールデコ
ジョージアン期
この頃の英国の国王であるジョージアン3世と4世から名を取ったジョージアン様式をあげることができ、この時代は、ジュエリーはいまだに王侯貴族と呼ばれる、社会の特定階級だけのものでしたので、ヴィクトリア期に見られる新興の市民階級は存在しておらず、ごく少数の例外を除いては、王侯貴族以外には顧客のいない時代でした。
当然のこととして、デザインや素材の面で奇抜なものがあるわけではありませんが、やがて来るヴィクトリア期の作品につながる先駆け的なものが多いですが、一番の特徴は使われている金が極めて薄いこと、すべての作品が手作りであること、それにダイヤモンドの使用が増えてくることになります。
金という貴金属の使い方こそ慎ましいですが、次のヴィクトリア期の大発展の基礎が作られた時代、それがジョージアン期であったともいえ、また、ほとんど機械をを用いないで人間の手の匂いのするジュエリーがジョージアン期といえると思います。
ヴィクトリア期
1837年6月、わずか18歳の少女ヴィクトリアが英国王に即位することになり、この可憐な少女が、以後の63年もの長きにわたって英国を支配し、その最盛期を作り上げようとは誰一人思いつかなかったでしょう。
ヴィクトリア女王は、英国史上で最長の63年という長い在位の間、女王として君臨するだけではなく、最愛の夫アルバート公との間に、実に9人もの子どもを成し、欧州各国の王室と縁戚関係を広く結び、同時にまた、自分の趣味と権威を通じて、当時のファッションに大きな影響を与えています。
1837年に即位してから最愛のアルバート公と死別する1861年までをヴィクトリア初期とし、この時期は、即位したばかりの若く美しい女王が、宮廷人のみならず、新興の金持ちたちのお手本であり、女王のなさることを真似る、これが最新のファッションでもあった時代です。
また、最も大切な素材であった金も、1848年にカリフォルニアでの金鉱発見や、その3年後にはオーストラリアでの金鉱発見に始まる世界各地でのゴールドラッシュにより、供給が大幅に増えて価格も下がったために、たくさん使うことが可能になり、ジョージアン期の薄い金細工は消えていきます。
さらに、時代の主人公の華やかさを受けて、カーボーションのガーネットや強い色の珊瑚が流行ったりして、この時代には華があります。
一方、1840年前後には、金メッキが登場し、1854年には、9金、12金、15金という新しい品位が公式に認可されます。
これは、18金という高い品位を維持してきた英国に、外国から低い品位の金製品が流れ込んできたのに対抗するための手段でした。
それだけ製品が流れ込むということは、そうした物を求める客層が生まれたということです。
そして、1851年には史上初めての万国博覧会がロンドンで開催され、ハイドパークに建てられた硝子張りの水晶宮には、文字通り、世界各国から集められた工芸品が展示され、その中に、多くの宝石やジュエリーが含まれていました。
ダイヤモンドでは、コーイヌール、ホープ・ダイヤモンドが展示され、英国のハント・アンド・ロスケル社をはじめとする多くの宝石商が作品を展示しました。
この博覧会は大成功で、その莫大な利益が計上され、その資金を使って作られたもののひとつが、今のヴィクトリア・アルバート美術館です。
この種の博覧会は、この後、世界各国で続々と開催され、その工芸部門の一部にジュエリーが含まれたことは、ジュエリーの発展に大きく寄与しました。
若く明るい女王を中心に、作られたジュエリーも大ぶりで明るい色彩に満ちていたこの時代を、ロマンティック・ヴィクトリアンとも呼びますが、まさにぴったりの表現であり、繁栄の頂点に達した大英帝国の女王を中心とする貴族たちの時代でした。
そんな最中の1861年、女王にとって最愛の夫であったアルバート公が突然に死去することになり、死因は公私にわたる過労といわれていますが、9人の子どもと残された、まだ42歳の女王にとってこれは大変な衝撃でした。
その証拠に、アルバート公が死去したウインザー城のブルールームと呼ばれる部屋は、1901年に女王自身が死去するまでの40年間、まったくそのまま手つかずの状態に保存されたと伝えられています。
そして、女王は異常なまでに長い喪に入り、濃い色の喪服を着る時期が続くことになり、そういう時代の中で、この喪服に合うジュエリーは生まれました。
金台に黒のエナメル、ジェットと呼ばれる漆黒の石、ボグオークと呼ばれる樫の埋もれ木などの作品が時代を風靡したり、昔からあった死者への髪の毛を編んだり、ロケットに入れたりした、いわゆるヘア・ジュエリーが再流行します。
エドワーディアン期
この時期のジュエリーを見て感じるのは、白い作品の時期ということがいえ、細いプラチナやダイヤモンドに白い真珠などで、金製品もありますが、むしろ例外で、白く華奢で上品な作品、それがエドワーディアン・ジュエリーといえます。
もうひとつの特徴は、極めて個性の強い作品を持った、宝石店が各地で産声を上げ今に残る名作を生み出したことです。
ガーランド・スタイルを生み出したカルティエや、アメリカの宝石商でありながら、欧州各国の王室御用達になったティファニー、大柄な作品に腕を見せたショーメ、伝統的でありながら、最新の流行を取り入れたラクロシュやフーケなどです。
彼らの作品はアンティーク・ジュエリーのなかで、署名入りのジュエリーとして、特別の扱いを受けていて、また、ロシアでは天才ファベルジェが活躍し、この時代ならではの優れた作品を数多く残しています。
エドワーディアン期の作品は、素材が日本人好みのプラチナを使い、手は込んでいるのですが繊細でわかりやすいデザインであることから、日本人の最も好むアンティーク・ジュエリーとなっています。
こうした良き時代も、第一次世界大戦とともに終わりを告げて、本物の貴族の時代は完全に終わりを告げることになってアールヌーボーというビッグジェネレーションが訪れることになります。